※このコラムでは、専門的な内容が含まれています。
人の生死は何を基準に判断されるのか。それは個人の解釈によって異なるものである。
例えば、妊娠した胎児を生きていると考えれば生きているし、脳死患者を死んでいると考えれば死んでいると解釈することもできる。ただ、法律ではその解釈を明確にしなければならない。そうでなければ法律問題を解決できないからである。
そこでここでは、法律的にみて、人(自然人)の「出生」はどのように解釈されているのかを見てみることにする。
人の「出生」の解釈は、民事と刑事で異なる。
民法第3条第1項では、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定されている。つまり、権利能力は出生から生じるというのである。
もう少し嚙み砕こう。権利能力とは、権利義務の主体となりうる能力のことである。例えば、コンビニでおにぎりを買う場合、コンビニと客との間で売買契約を結ぶことになる。そうなると、客はコンビニに対し「おにぎりを引き渡せ」という権利が生じ、同時に「代金を支払う」という義務が生じる。これは客が、権利を得たり義務を負ったりできる能力を持っていることになる。これが権利能力である。
ここで問題となるのは、民法でいう「出生」の定義である。胎児の段階で「出生」を認めれば、胎児も契約を結べることになる。だがこれは現実的にあり得ない。だから民法でいう「出生」は、母体から完全に分離した時というのが通説である(全部露出説)。
だが、問題もある。胎児の段階で父親が他人の不注意により死亡した場合、前述の「出生」の定義から言えば、その胎児は相続権も損害賠償請求権も無いことになる。仮にその父親が、胎児が生まれるまで生き延び、胎児の生まれた後に亡くなった場合、生まれた子は相続権も損害賠償請求権も取得することができるだろう。母親の胎内では胎児として存在していながら、生まれたのが父親の死亡の後であるということのみで何らの権利も取得できないのは不公平である。
そこで民法では、相続・不法行為に基づく損害賠償請求権・遺贈に関しては例外として生まれたものとみなす規定が置かれている(民法721条、886条、965条)。これで胎児にも相続権や損害賠償請求権が認められるわけだ。なお、「生まれたものとみなす」の意味については、解除条件説と停止条件説があるが、その説明はここでは割愛する。
次に刑事である。
Xが、母体から一部露出した胎児を殺害した場合、Xは殺人罪(刑法第199条)に問われるのか。
全部露出説に従えば、胎児は母体から完全に分離していないのだから人としてはまだ認められず、胎児に対する殺人罪は適用されない。もし、Xが母親の依頼を受けて、母親の胎内で胎児を殺害したときは、Xは堕胎の罪(刑法第213条)に問われることになる。これは胎児が全部露出していない場合にもいえる。胎児がほぼ全身を露出させた状態で、Xが母親の依頼を受けて胎児を殺害した場合、Xはやはり堕胎の罪を負うにとどまるのである。これでは、人の生命に対する保護が十分とは言えないだろう。
そこで、胎児の身体の一部が母親から露出した時が「出生」であると解釈するのが刑事での判例である(一部露出説)。上記の事例でのXは、殺人罪に問われることになる。
民事と刑事とで解釈の異なる「出生」の定義であるが、これが現在の法律実務である。ただ、全部露出説と一部露出説、そのどちらにも合理的な面がある反面、批判もある。法律学者はそれぞれの説を研究し、発展させていく。いずれは法律実務も変わるのかもしれない。

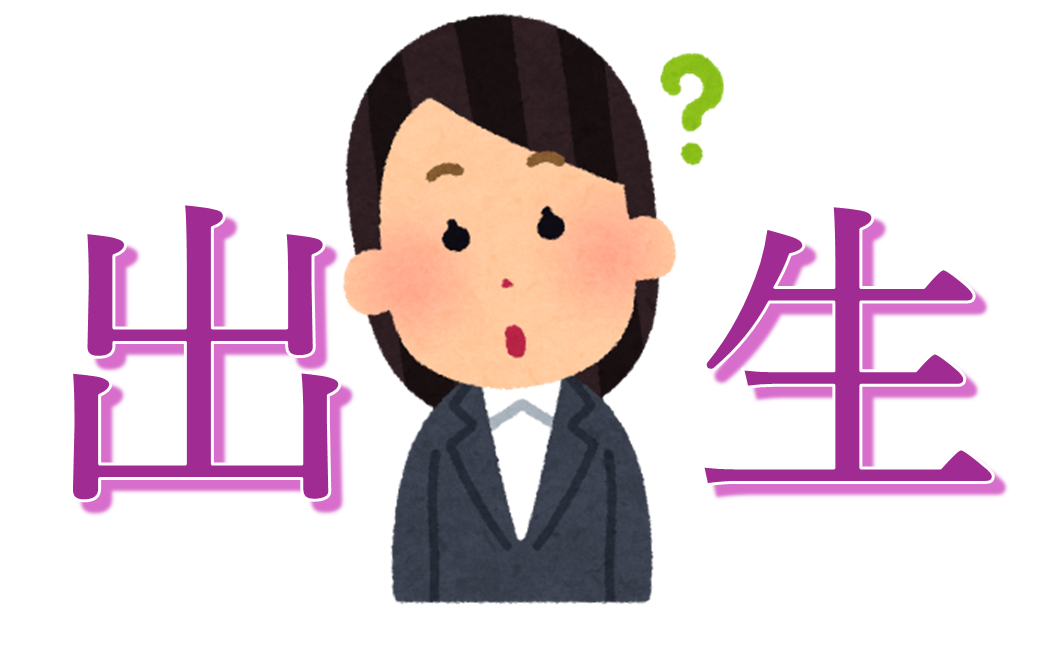
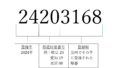

コメント