行政書士になる最短の道は、行政書士試験を受験することです。しかし、合格することは簡単ではなく、合格率は13.98%(令和5年度)です。平成15年度は過去最低の2.62%を記録しました。行政書士試験の合格率は平均10%前後の狭き門です。
それでも法律系の資格の中では比較的取りやすいといわれていますが、しっかり勉強しないと合格は厳しいでしょう。
なぜ法律系の試験は合格率が低いのか。行政書士試験に合格するには? 私の経験談を基に、考えてみたいと思います。
まず、法律系の国家試験の合格率が低い理由の一つに、国民の権利に重大な影響を与える仕事であることがあげられると思います。生半可な法律知識で依頼人にアドバイスすると、依頼人の権利が侵害されることになりかねません。
例えば、借金を多く抱えて亡くなった方の相続人に対し、熟慮期間(相続放棄できる期間)は6か月であるとアドバイスをし、4か月目に相続放棄の手続きをしたとします。この手続きは家庭裁判所に対して行うのですが、家庭裁判所は相続放棄の申し出を受け付けてくれないでしょう。なぜなら、法律上の熟慮期間は3か月と定められているからです。熟慮期間を過ぎてから手続きをした相続人は、相続放棄できずに多くの借金を負うことになってしまいます。これは明らかに、誤ったアドバイスをした者の責任です。
このように、どんな士業であれ法律を扱って仕事をするということは、大きな責任が伴うのです。正確な法律知識、判例知識などを試し、その職業に対する適性があるのかを判定するのが法律系試験です。
次に、行政書士試験を見てみましょう。
行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業務とします(行政書士法第1条の2)。つまり、役所などに提出する書類の作成、契約書や相続関係書類などの作成を業務としています。当然、行政書士試験もこの業務を行う適性があるのかを判定する内容となっています。
★行政書士試験
認定:総務省
受験資格:なし
試験日:毎年11月の第2日曜日
試験方式:五肢択一式・多肢選択式・40字程度の記述式
試験科目:五肢択一式
基礎法学・憲法・民法・行政法・商法・会社法・一般知識等
多肢選択式
憲法・行政法
記述式
民法・行政法
合格点:180点以上(法令等科目で50%以上、一般知識等で40%以上の得点)
行政書士試験は、他の法律系試験とは違い、口述試験や論文試験はありません。そのかわり、基礎法学や一般知識が試験科目に採用されているのは行政書士試験だけです。
基礎法学があることによって、法律初学者でも受験勉強に入りやすいでしょう。また、国は受験者の法律基礎知識を試すことによって、幅広い年齢層の方や他業種の職業の方でも法学の基礎知識を確認することができます。その意味では、だれでも受験しやすい試験といえます。
次に、受験者を苦しめるのが一般知識です。具体的には、政治経済社会・情報通信技術・個人情報保護法・文章理解などが出題されます。文章理解は国語のような問題で、毎年出題されているので対策は立てやすいです。ただ、その他はどんな問題が出題されるのかは分かりません。年度によって個人情報保護法が出題されなかったり、情報通信技術が出題されなかったりします。一方で、最近話題のニュースが出題されたり、地理の問題や外国の歴史が出題されたりします。一番の対策法はテレビのニュースや新聞を日頃から読むことですが、それだけでは対策は十分ではありません。重要だと思って注目していたニュースは出題されないことが多いです。
一般知識等は対策が立てにくい上に、40%以上(24点以上)の得点をしないと、全体として180点を超えていたとしても、それだけで不合格となってしまいます。ではどうやって点数を取ったらよいのか。私が行った対策法をこっそりお教えします。
まずは対策しやすい文章理解から勉強しましょう。文章理解の出題形式は以下のように分けられます。なお、~式は筆者が考えたものです。
□ 組み合わせ式・・・四角で隠された部分の語句や文章の組み合わせを選択肢から選ぶ問題。
□ 組み入れ式・・・提示された文章が本文中のどこに入るのかを選択肢から選ぶ問題。
□ 入れ替え式・・・バラバラの文章の順番を選択肢から選ぶ問題。
□ 理解式・・・特定の単語や文章の意図を読み取って、適当なものを選択肢から選ぶ問題。
おおむねこのような種類がありますが、それぞれの解き方さえ覚えてしまえば簡単です。例年3問出題され、1問4点ですから、一般知識で12点獲得できることになります。あと12点取れば一般知識で不合格となることはありません。
その他の一般知識の対策法としては、予備校の予想問題を解く方法、公務員試験の参考書を詰め込む方法などがありますが、大半は出題されません。それよりも法律系科目に力を入れたほうが良いでしょう。では、どのように解くのか。その他の一般知識でも種類を分類することができます。
□ 一般常識型・・・学生時代に習った知識を問う問題。(例:日本の最南端の島は?)
□ 一般常識難問型・・・高校や大学でしっかり学習しないと解けない問題(例:1960 年代以降の東南アジアに関する妥当な組合せはどれか?)
□ ニュース型・・・最近のニュースに関する問題。(例:トランプ大統領が再選したのは何月?)
□ 法律型・・・個人情報保護法や公文書管理法などの知識を問う問題。
□ 情報型・・・情報通信技術の知識を問う問題。
おおむねこのような出題です。私はこのように解きました。
● 一般常識型・・・学生時代を思い出して解答。(対策:クイズ番組を見る)
● 一般常識難問型・・・消去法で解く。分からなければ捨てる。
● ニュース型・・・消去法で解く。(対策:ニュースや新聞を読む)
● 法律型・・・参考書で知識をつける。
● 情報型・・・参考書で知識をつける。
この中の3問でも正解すれば、文章理解と合わせて24点取れますので、一般知識等で足切りとなることはないでしょう。とにかく分からなくても解答することが絶対です。まぐれで正解することもありますからね。
後は、予備校の参考書で知識習得 → 過去問を解く → 解けなかった問題の知識を参考書で補充 → 過去問を解く→ 過去問を完璧にする(注:選択肢ごとにどこが誤っているのか指摘できるようにする) → 予備校の予想問題を解く → 解けなかった問題の知識を参考書で補充 → 予想問を解く → 予想問を完璧にする(注:選択肢ごとにどこが誤っているのか指摘できるようにする)
私はこれで合格しました。予備校の参考書や過去問、予想問は市販されていますが、なるべくひとつの予備校出版のものに絞ることです。様々な予備校の本を買い漁っても混乱するだけですし、費用の無駄です。
ちなみに基礎法学は捨てても構いません。正解できればラッキー!という気持ちで試験に挑んでください。
ここまで私の学習法を解説しましたが、これがすべてではありません。自分に合った学習法を見つけることが合格への第一歩です。これから行政書士試験を受験される方は、私の学習法を参考にしながら、自分の勉強法を見つけてください。応援しています!!

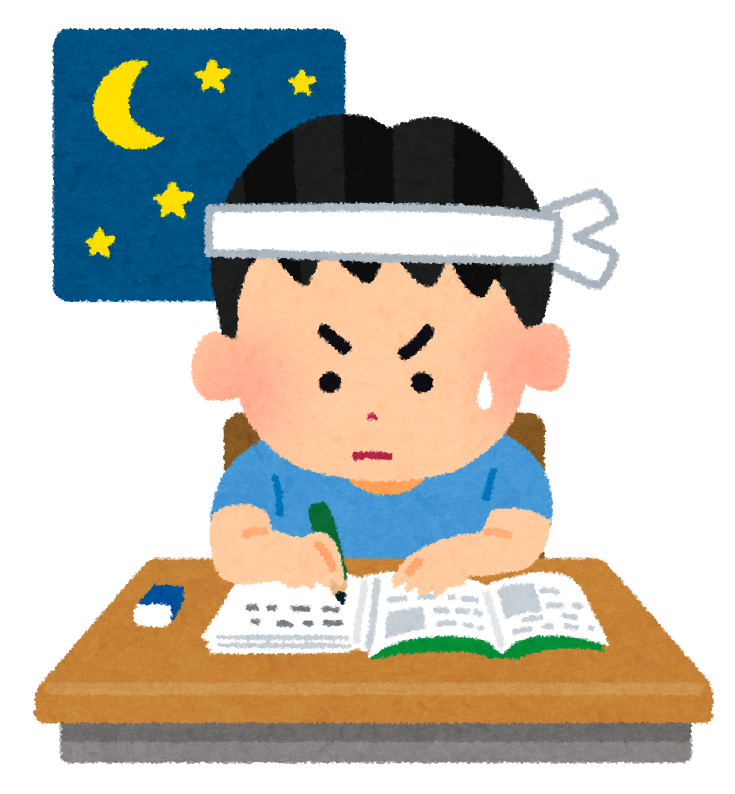

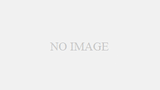
コメント